「株分けをしたら葉がしなしなになった」
「株分けをしたら育たなくなった」
こうなる前にお読み下さい。

ビカクシダイアリーへようこそ。
この記事では、私が経験したビカクシダ・ビフルカツムの株分け後の不調と、その後の経過について書いています。
株分け前の観察

もともと、ポットで購入した株でしたが、すでに貯水葉が張り出していて、はっきり言って密生状態です。胞子葉が放射状に伸びており、理想的な貯水葉と胞子葉の組み合わせも、見当たりません。
貯水葉の間を胞子葉が無秩序に伸びています。成長点も複数あり、ごちゃごちゃしています。
とりあえず、成長点ごとに、切り離し、板付けにすることにしました。
3つに分けました。

真ん中の株は特に根が少ないです。
板付け後の観察
3つに分けられましたが、それぞれあまり元気がありません。

根の量が圧倒的に少ないのがあります。左のコルク付けにした株です。成長点のようなのが見えますが、育っている様子はまだ見られません。
真ん中の焼杉板に付けた株は、葉の付け根が、貯水葉によって、ねじ曲げられていて、しかも細いです。
拡大写真です。

葉の付け根のところが傷ついていて、これ以上の成長はなさそうなのでカットすることにしました。

上の写真の右側の、100均のコルクボードに付けたのは、後日アカシアのカッティングボードに付けかえました。


アカシアのカッティングボードに板付けした株が、3つの中では一番元気がいいです。ですがこれにも根元が傷ついた葉がありましたのでカットしました。

写真ではよく写っていませんが、貯水葉が新しい葉をグイと、左向きに押し曲げられていて、正面を向けても葉が左をむいています。根元に成長点がみられますので、今後、順調に成長してくれることを願います。
ビカクシダの不調の原因
根が少ない
株分けをして、板付けにして、一週間後、ますます元気がなくなってきました。
今回のように根が少ない株は水分を吸い上げる力も弱いようです。
葉の付け根が細く、傷ついている
貯水葉に圧迫されていた葉の根元は細くてその重さに耐えるだけの力がなく、だらりと垂れています。新しい胞子葉だけがピンとしていて、それがせめてもの希望です。
結論:株分けはビカクシダにとっては大きな怪我をしたような状態なのではと思います。強引な株分けはリスキーです。
株分けの季節を間違った
今回、強引に11月に株分けをしてしまいました。冬場はビカクシダは成長が遅くなりますので、寒くなる前の株分けはお勧めしません。5月~8月に行いましょう。
元気のない株のお世話
ビカクシダは風を好みますが、それは元気な状態のときであって、葉がしなしなしている時は、そっとして、ひたすら根が張って水を吸い上げて、新しい葉の展開を待つしかすることがないようです。頑張って欲しいです。
室温は他のビカクシダと同じく、18度以上キープが目標。夜間も10度を下回らないようにヒーターで部屋を温めています。葉水は一日に3回くらいしています。基本的に水苔が乾いたら潅水ですが、水を吸いやすいように湿らせ気味にしています。あまり風が当たらないところにぶらさげています。
このやり方が正しいのかどうかは、結果がでてからしかわかりません。
株分け後1ヶ月を過ぎて
辛うじて生きながらえている状態で、著しい成長はみられません。
季節も秋に入り、成長のスピードも緩やかになってきているのも理由の一つでしょうか。

左の二つは元気がないでしょう?回復するんでしょうか?
ところで、焼杉板とアカシアのカッティングボードはDIYで穴をあけました。
株分けの要領と失敗しないための注意
株分けするときは、成長点を傷つけず、ある程度根っこを残してあげることは大切です。また、根を分けるときは成長点裏の一番太い根に傷をつけないように気をつけてください。
今回のような特徴の株は、欲を出さず、一番育っている株の成長点を中心に板付けするか、せいぜい二分割までに止めておくべきでした。
後から成長の邪魔になる成長点を潰して、残した方に重点をおいて育てる方が生き残る可能性は高いはずです。
又は、株分けはせずに、そのまま板付か苔玉にしてしまうという選択肢もあったはずです。
全部の成長点を生かそうとして、逆に全部を失うかもしれないというリスクを背負ってしまいました。ビカクシダには、本当にかわいそうなことをしてしまいました。
また、ビカクシダは冬場は成長のスピードがガクンと落ちるようです。なので、株分け後は特に冬の寒さは回復には悪影響だということが、初めての冬越し経験でわかりました。
株分けをするタイミングは「春~夏」つまり5月~8月ですね。
私は無理やり11月にやってしまいました。失敗の原因の一つです。痛い!!
寒い季節に新しい株を入手した時は、そのままの状態で板付けして、暖かくなるまで育て、暖かくなって、それぞれの成長点のまわりの葉が大きくなってから株分けをするべきだと思います。
この経験は今後に活かしていきたいと思います。
株分け後3ヶ月を過ぎて

右のは辛うじて元気がありますが、真ん中と左は元気がありません。
特に左のは葉がしなしなで野菜なら棄てるレベルです。でも可哀想なので諦めずにお世話をしています。
真ん中と右のには成長点がありますので、春になったら新しい葉が展開してくれて、見違えるようになってくれるのではないかと、期待しています。
左のには成長点すらありません(涙)
下が成長点の写真です。

株分け後5ヶ月を過ぎて

右のカッティングボードの株だけ成長しているようです。胞子葉が大きくなってきました。また、新しい成長点も膨らんできています。

左のコルクに板付けした「しなしな」の株は、4枚あった葉から1枚が自然に脱落していよいよクライシスな状態です。
でも、まだ、諦めてはいません。新しい成長点の現れを待っています。
株分け後6ヶ月を過ぎて
暖かい季節になりました。

右のカッティングボードの株は葉が元気になって、成長点のモフモフもみえてきました。今年の夏が楽しみです。

真ん中の、焼杉板の株は元気がなく、いったんこんなになった葉は、回復の見込みはないでしょう。新しい葉が育って葉が入れ替わるまで待たなければなりません。
葉が入れ替わる為には成長点がないといけませんけど、現在のところ、こんな⇩感じです。いくつか成長点があり、将来性はあります。

一番心配なのは左のコルクの株ですが、まだ、成長点が見られず、「ん~」っていう感じです。

真ん中に見える突起のような物は、残念ながら成長点ではなく、硬い茎の切れ端のようなものです。実は、初めにこれを成長点だと勘違いしていたのです(失敗)
やはり、この株は分割せずに大きい方の株にくっつけておくべきでしたね。
でも、まだ諦めずに、お世話を続けていきます。
株分け後6ヶ月半を過ぎて
前回の写真からまだ半月しか経っていませんが、報告させてください。
五月も末になり気温も上がってきました。
カッティングボードに板付けした株の貯水葉がはっきりとしてきました。また、胞子葉の先端も割れてきて、ビフルカツムらしさがでてきました。
新しい貯水葉が、右側に展開してくれたら、かっこよくなりますね。

他の2株も「がんばれ~」ヾ(*´∀`*)ノ
株分け後7ヶ月を過ぎて
焼杉板の株に動きがでてきました。

成長点の動きが活発になってきて、小さい胞子葉も次々と出てきています。
モフモフが貯水葉になればいいな、と思います。
新しい葉が大きくなったら、下向きのしなしなの葉をカットしよ~っと。

コルクの株は変化なしです。でもまだ生きてます。
株分け後8ヶ月を過ぎて
今回は大きな変化の月となりました。
- カッティングボードの株を板付けしなおした
- 焼杉板の株のしおれた胞子葉を落とし板付けしなおした
それぞれお見せします。
カッティングボードの株を板付けしなおした
最初に株分けをした時点で左を向いていました。葉っぱ同士が押し合って、茎の根元がぐいと曲げられていた状態でした。
今回は貯水葉が大きく成長してきましたので、貯水葉の下に水苔を詰め込み、株の左側にも水苔をこんもりと盛って、さらに葉の向きが前になるように成形しなおしました。
ビフォーアフターの写真です。

この株は、テグスを切ってもしっかりと板に吸着していて、板から外してみると根と水苔が同化してスポンジのようになっていました。
焼杉板の株のしおれた胞子葉を落とし板付けしなおした
先月やや伸び始めていた胞子葉がどんどん大きくなってきました。

下の3枚の萎れた葉は、回復することはありませんでした。
萎れた理由は、①株分けの時に根が少ないか②傷ついたかですが、いったんこうなると、回復しないのがわかりました。
独特の水気のないボテッとした葉に触れる度、失敗したなと思います。
しかし!!
今日で辛い思い出とさよならします。
この焼杉板の株もいったん解いて新しい板につけます。
ビフォーアフターの写真です。

萎れた3枚の葉をカットして、新しい水苔で、新しい板につけなおしました。
すっきりして、あの傷だらけの株分け被害の姿はもうありませんね。
しかし、こちらの株は、テグスをほどいた時、板から簡単に外れて、最初に板付けした時のベラボンや水苔がバラバラっと落ちて、根が張っていなかったことがよくわかりました。
なので、貯水葉も展開していないし、胞子葉の成長も遅かったのですね。
これからは、どんどん成長してくれることでしょう。
では、記念写真です。

左のコルクの株は相変わらずです。成長点もありません。( ;∀;)
株分けで元気がなくなった株のまとめ
最初のあたりでも書きましたが、株分けの失敗の原因と失敗の影響は
- 株分けをしたら根が少なくなってしまった
- 成長点と思ったらそうではなかった
- 秋ごろ株分けをして、冬場は成長が止まってしまった
つまり、株分けを成功させるには、上の逆をすればいいわけです。
夏の初めに、根っこを傷つけないように、ある程度量を確保して、活発に動いている成長点を中心に株分けをする。
もう失敗しないぞ~!!
失敗から10ヶ月で回復!!
いったん傷ついた株は、回復するのに根気よく付き合わなければいけません。
でも、諦めずにお世話を続けると、応えてくれることがわかりました。
しかし、成長点がないところには回復もないこともわかりました。
⇩株分けから10ヶ月経過した画像です。

左のコルクの株はとうとう葉が脱落してしまいました。(: :)/~
真ん中の株はようやく貯水葉が展開してきて、ビカクシダらしくなってきました。
右の株は2ヶ月の間に、古い貯水葉の上から、左、右と次々に緑色の貯水葉が成長して、立派になりました。
最後までおつきあい下さり、ありがとうございました。
この記事が株分けに失敗した方への励ましになれば幸いです。
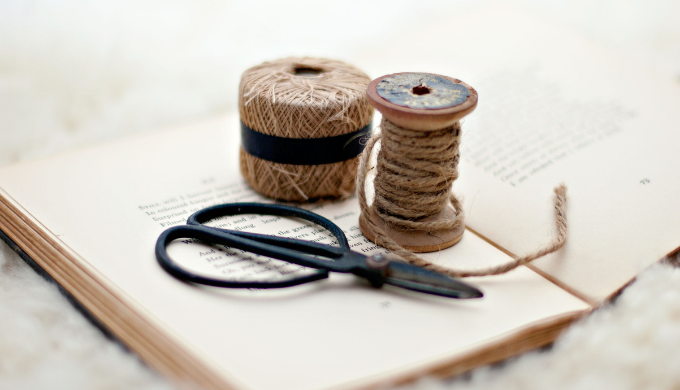



コメント