「コウモリランとビカクシダ、どちらで呼べばいいの?」と悩んでいる方への記事となっています。これを読むと、少し物知りになって、誰かに話したくなるかもしれません。
ビカクシダイアリーへようこそ。
この記事は「コウモリラン」と「ビカクシダ」の名前の由来と、それをめぐる雑学について書いています。お暇な人はお付き合いください。
そもそも、「コウモリラン」なのか、「ビカクシダ」なのか?

どっちやねん?

どっちやねん?
答えから言うと、どちらも正解です。
コウモリランと呼ばれてきた理由
その葉が「コウモリの羽」に似ているので「コウモリラン」と呼ばれてきたのですね。名付けた人は「蘭」だと思ったんでしょうね。ここから先は私の想像ですが、野生のコウモリランは熱帯地域の樹木に根をはって着生しています。時には一本の木にびっしり着生しています。その姿が木に密集してぶら下がっているコウモリに似ていたのもあるのではないかしら?

なんだか可愛いですね。フルーツコウモリです。羽を広げるとこうなります。

「ラン」と「シダ」について
さて、「コウモリラン」というので初めてその名前を聞いた人は「蘭」かと思うところですが、これは実際は「シダ」なのです。
蘭は花を咲かせ、種ができます。ところがコウモリランは花を咲かせません。そのかわり胞子で子孫を増やします。
もう一つの方法として株でも増やせますが、それは、蘭もコウモリランも同じです。
ここからはビカクシダと呼びましょうか。
ビカクシダには2種類の葉の形があり、水分や栄養分を貯めておく貯水葉と、光合成や胞子を作る胞子葉があります。
写真は他のシダ類の胞子ですが、これと似たような茶色い胞子を葉の裏に作ります。植物学的には間違いなく「シダ」なんです。

あら、シカじゃないの?

シダだよ


これが我々が普段思い浮かべる「シダ」の胞子ですね。中学生の時に教科書で見ましたっけ?
ビカクって?何?
ビカクというのは「糜角」と書きます。意味は「なれしか」の角という意味です。
「なれしか」というのは「大鹿」のことです。「大鹿」と呼ばれているのは、ヘラジカ、アカシカ、ワピチです。
では、それらの画像を見てみましょう。

うわっ、大きいですね。これはヘラジカです。角も立派です。

2枚目の画像はアカシカです。ヘラジカの角より細身です。

3枚目の画像はワピチです。角が太くて立派です。
なるほど。納得ですね。大鹿の角はビカクシダの葉によく似ています。というより、ビカクシダの葉が大鹿の角によく似ています。ナイスな命名でしたね。
ビカクシダの学名はPlatycerium(プラティケリウム)で、和名が「糜角羊歯」です。
読み方は「ビカクシダ」です。
まとめ
私たちの暮らしの中では、「コウモリラン」も「ビカクシダ」も両方つかえます。たとえば、通販サイトを見るとわかりますが、流通においては「コウモリラン ビカクシダ」と併記されています。どちらかというと、コウモリランが先にきて、あとからビカクシダと書いてあるのが多いです。
それだけ「コウモリラン」という名前が愛されているということですね。
実際「ビカク」ときいて、大鹿の角を連想する人はほとんどいないでしょうから、たとえ、学名の和名が「ビカクシダ」であっても「コウモリラン」の名前が消える事はなさそうですね。

上はクリスマスのトナカイの飾り物です。
部屋に鹿の頭部はちょっと苦手な方もおられると思いますが、ビカクシダなら誰もが楽しめることでしょう。
あなたも、コウモリラン、ビカクシダを育ててみませんか?
では、今回はこのへんで。
最後までお読み下さりありがとうございました。
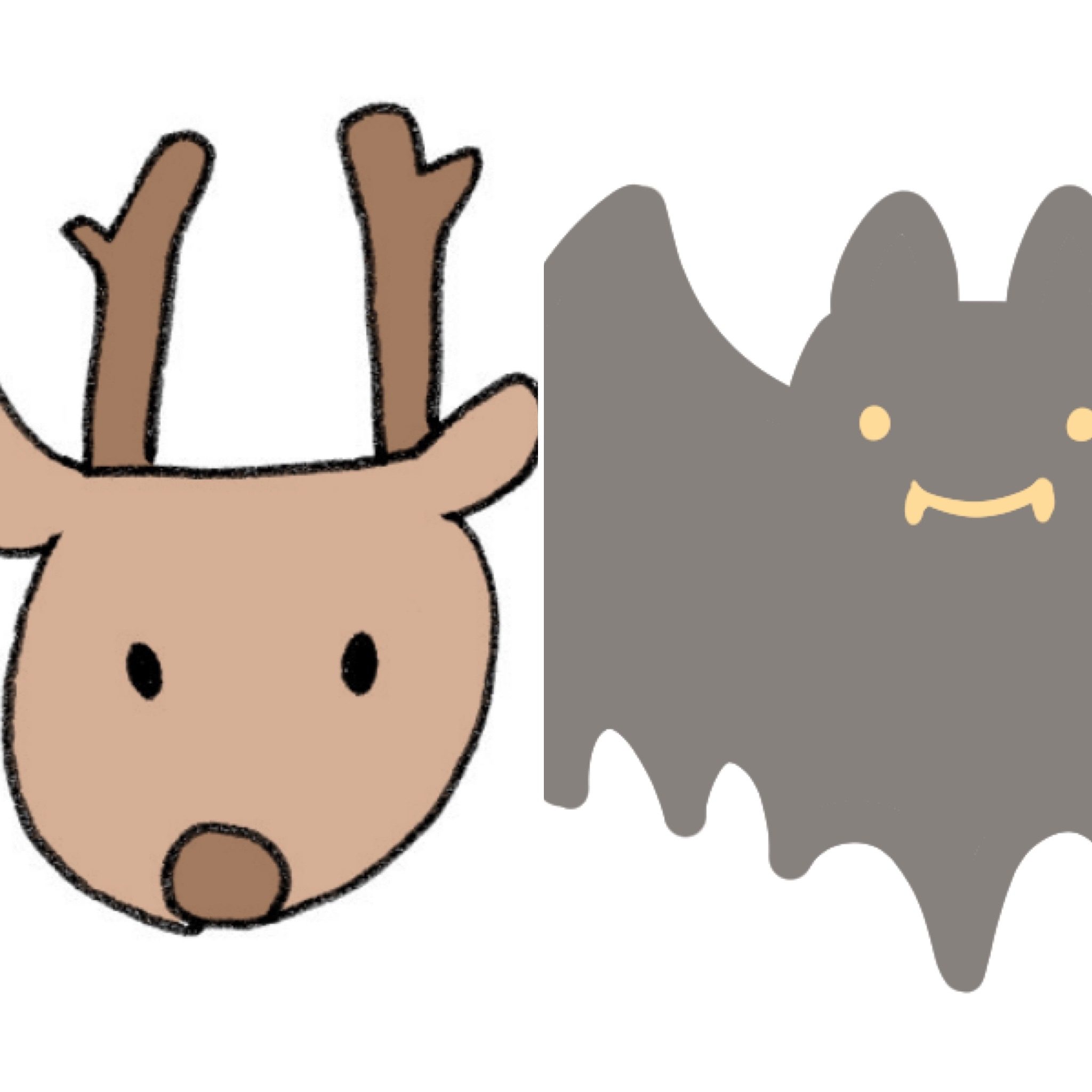

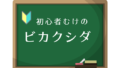
コメント